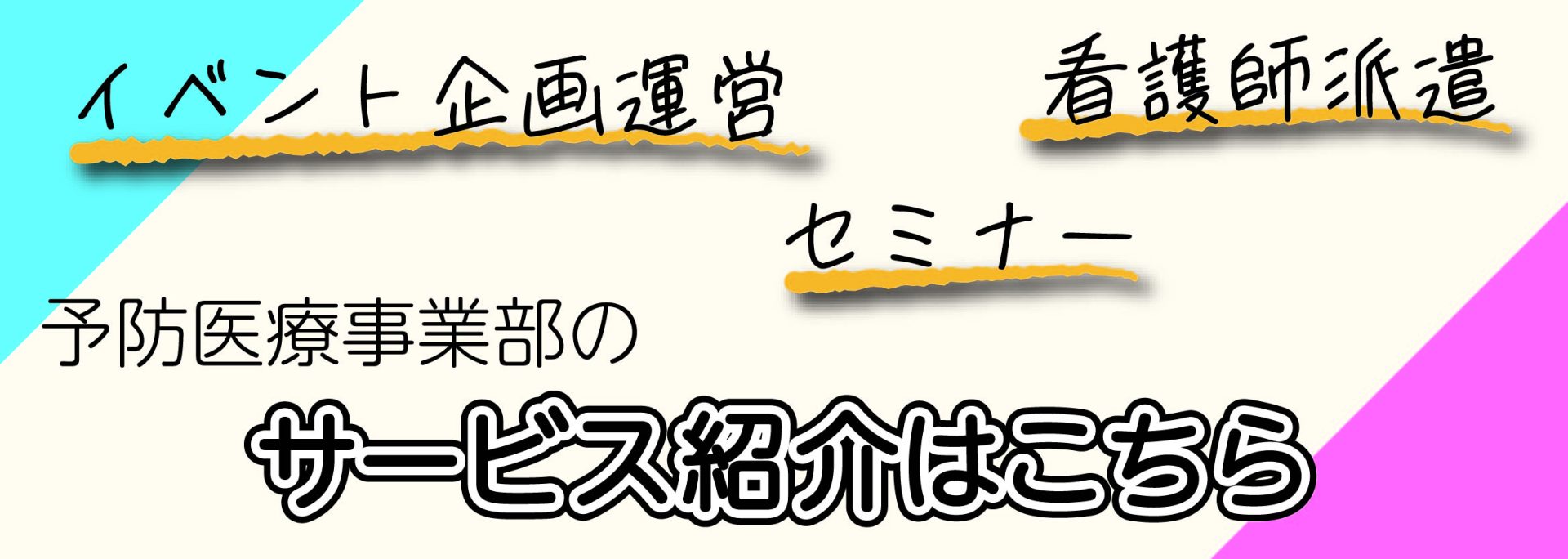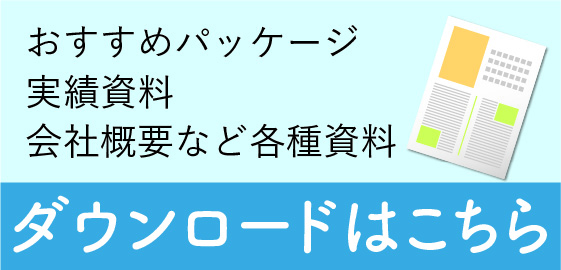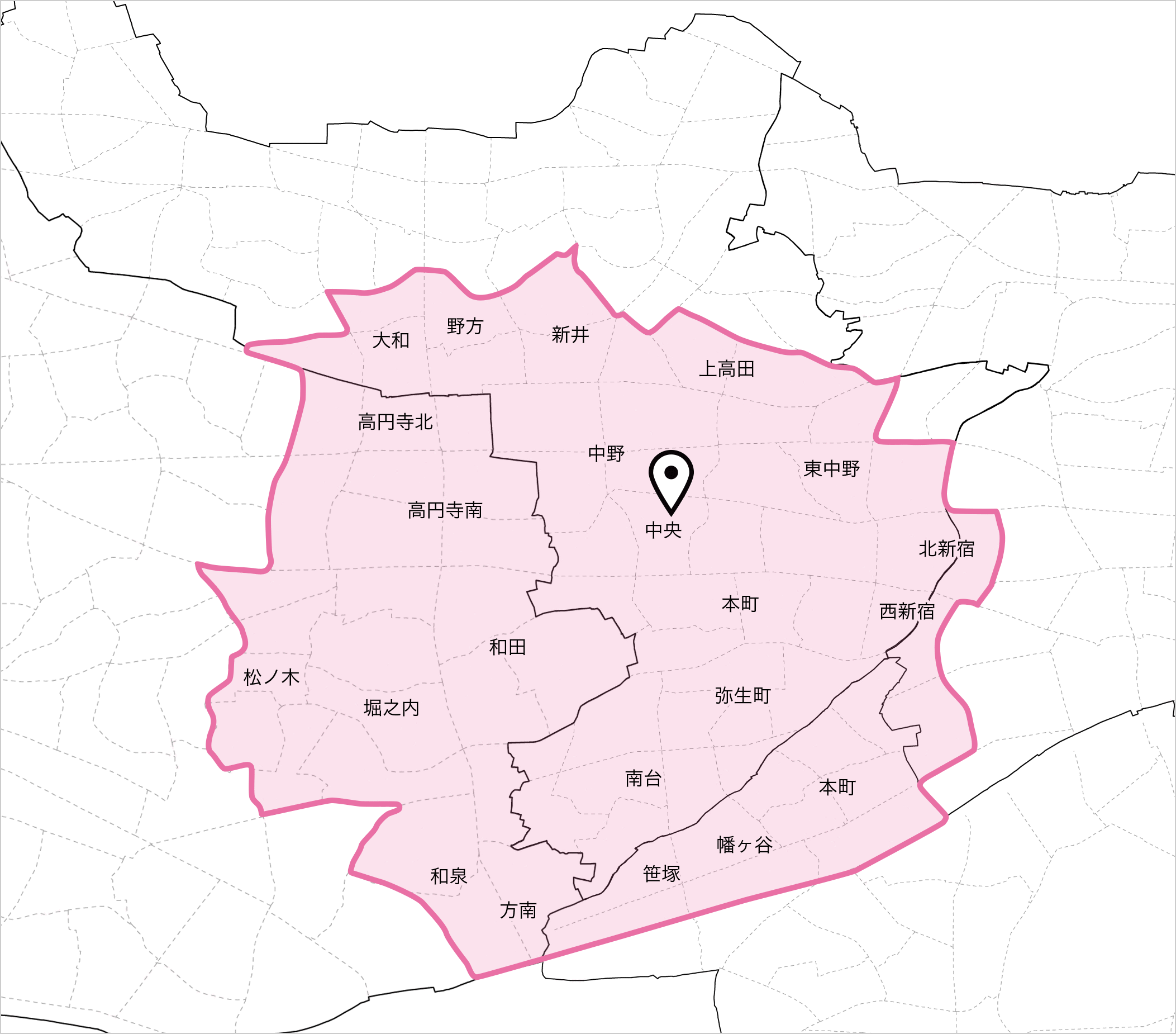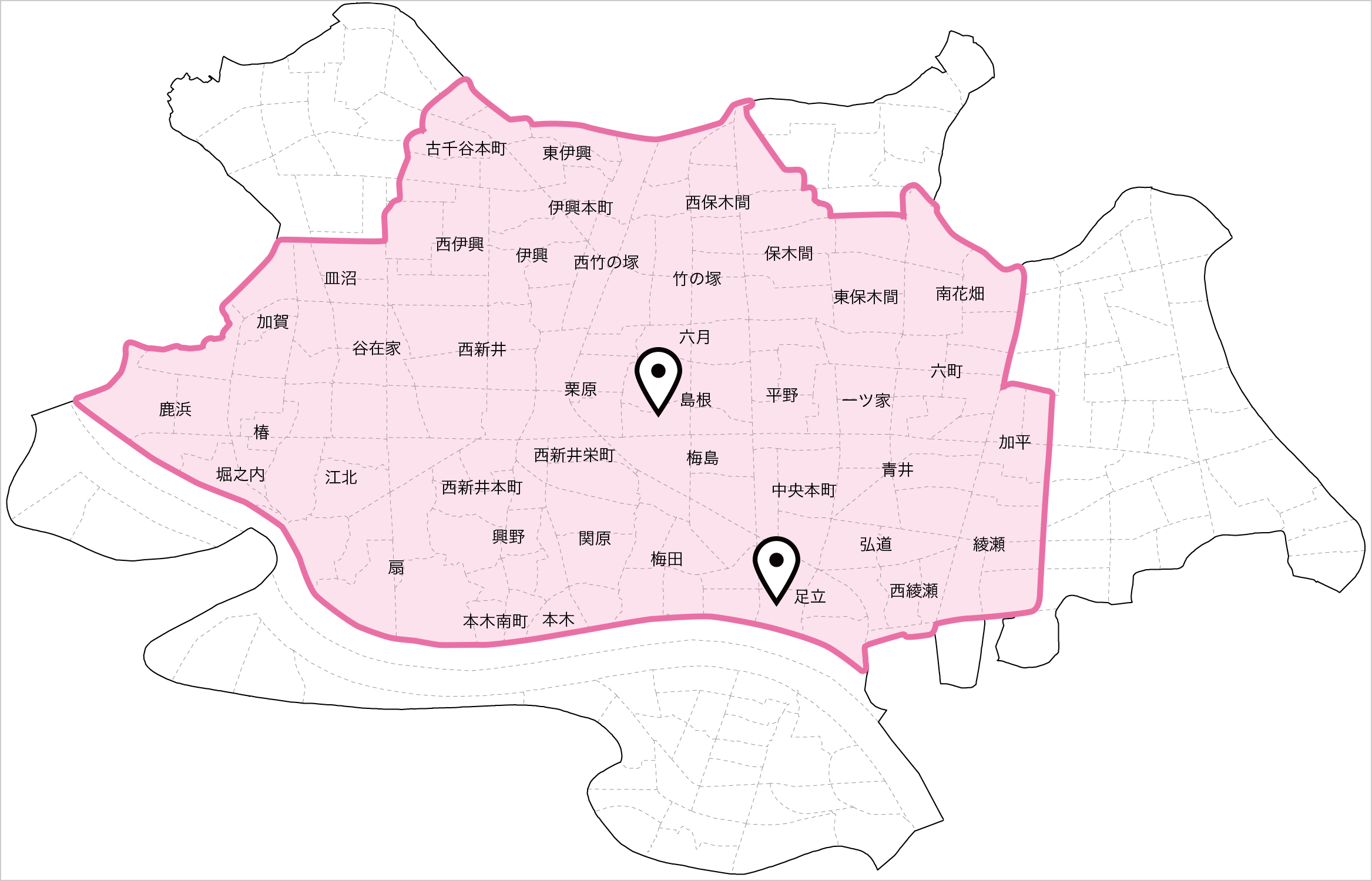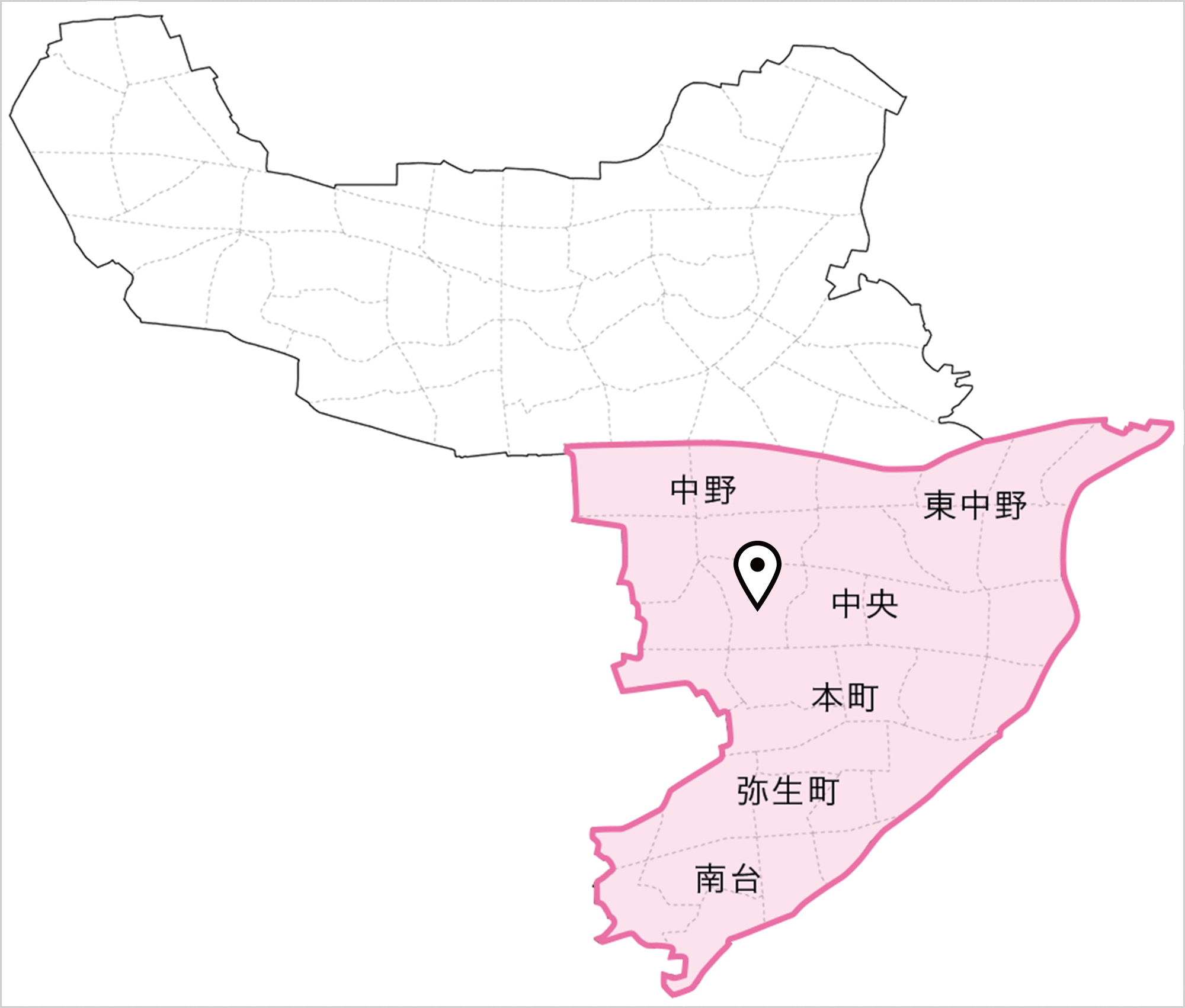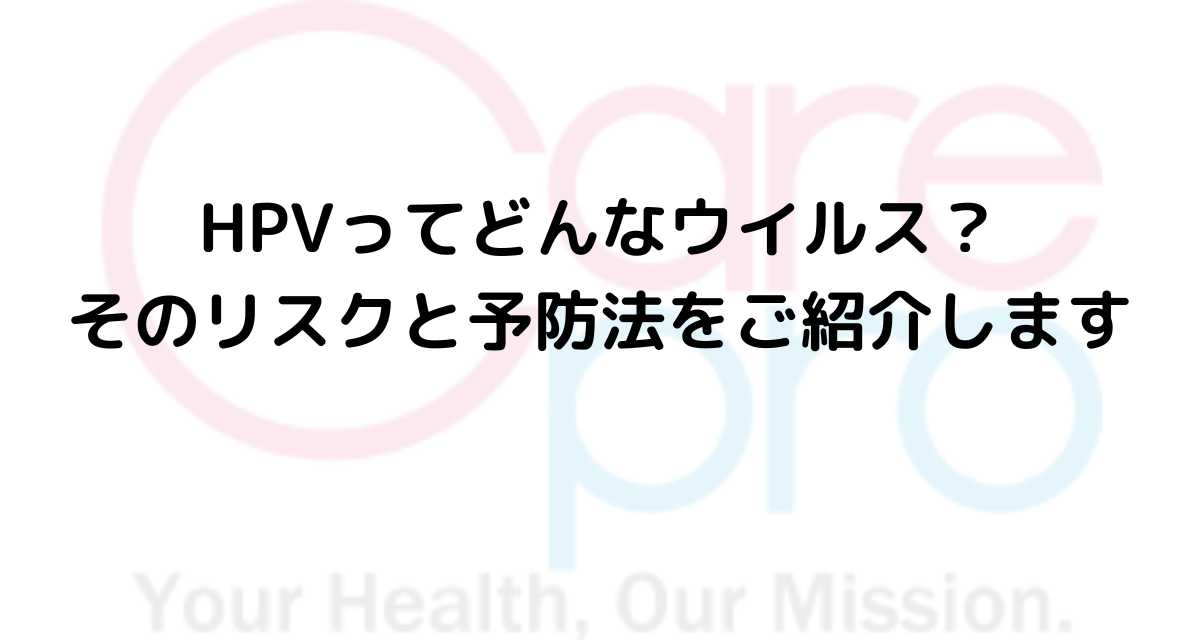
HPVってどんなウイルス?そのリスクと予防法をご紹介します
公開日:2023/01/12 最終更新日:2023/10/20
こんにちは。この記事はケアプロ予防医療事業部の臨床検査技師スタッフが監修しています。
近年、「子宮頸がん」の一般での認知が広がってくるにつれて、「HPV」という単語も有名になってきました。
そのため「HPV」と聞くと、つい「子宮頸がん」だけを連想する方が多いと思います。
しかし、実はHPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスは、
子宮頸がんだけでなく、尖圭コンジローマや中咽頭がん、肛門がんなどの原因にもなるということをご存知でしたでしょうか?
一口にHPVといっても、それにはさまざまな型があり、それぞれがどんな病気を引き起こすことが多いのか、には特徴があります。
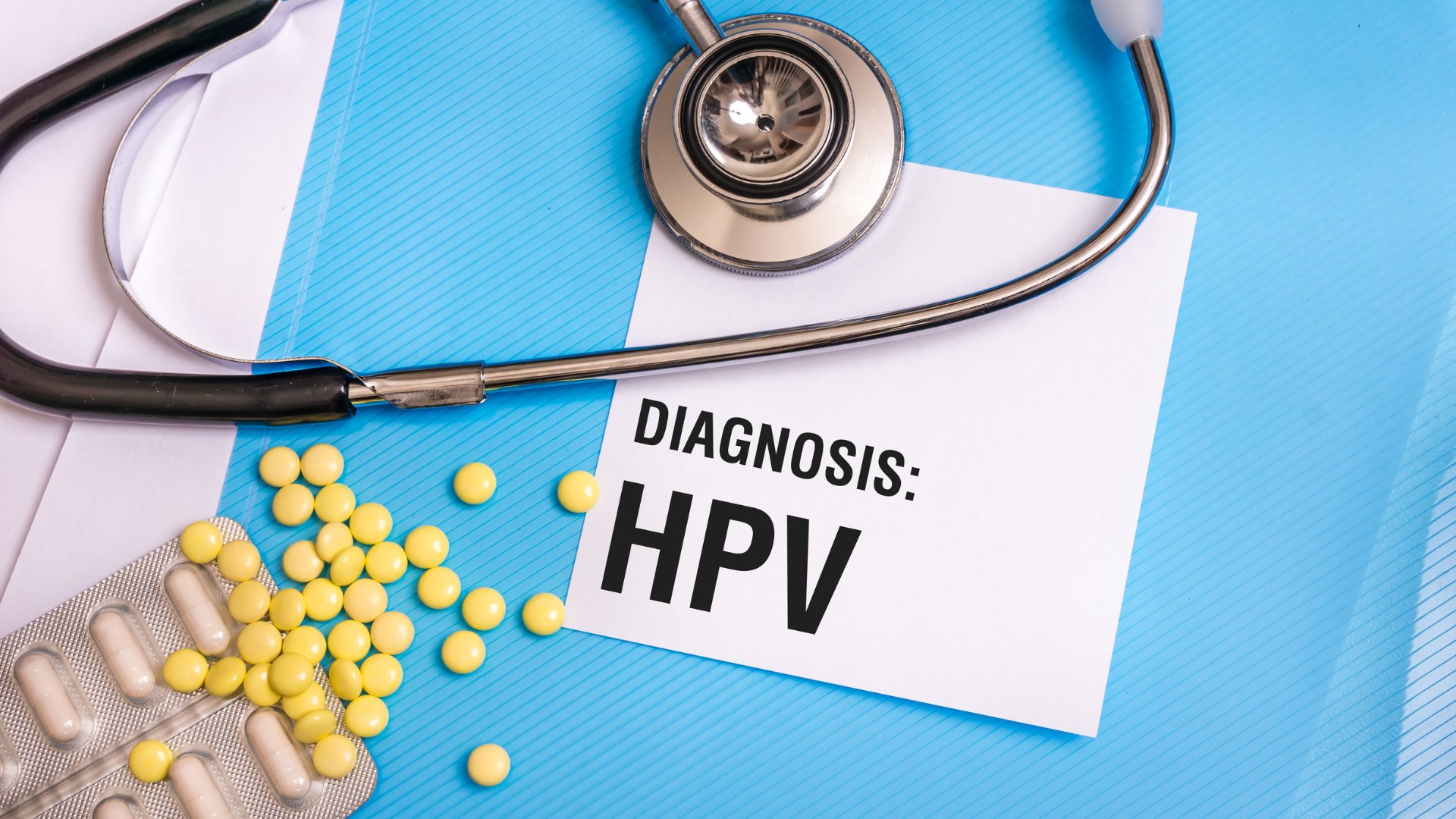
とはいっても、HPVを原因にし、近年の患者や死亡者数が増加傾向の最もリスクが高い病気は「子宮頸がん」であることには変わりありません。(他のリスクが低いわけではありません)
そこで今回の記事では、臨床検査技師という医療の有資格者が監修し、「子宮頸がん」に焦点を当ててHPVについてわかりやすくご紹介していきます。
「ウイルス」と聞くとなにやら恐ろしい話なのか、と思いがちですが、正しい知識と対処法を身につければ、リスクは最小限にすることができます。
ぜひ、この記事を通じて、HPV(ヒトパピローマウイルス)の予防と対策をご覧になっていっていただければと思います。
HPVとはどんなウイルスなの?
すでに何度か登場していますが、
HPVの正式名称は、「ヒトパピローマウイルス(Human papillomavirus)」です。

このウイルスは性行為で感染するウイルスで、遺伝子型は150種類以上もあります。
HPVの生涯感染率は性活動を行う女性の50〜80%以上で、誰もが1度は感染する可能性があります。
そのため、決して感染することが珍しいウイルスではないことが注意点です。
とはいえ、感染してもからだの免疫力で2年以内に排除されるといわれています。
しかしごく一部の人は、ウイルスを排除できなかったり、接触する頻度が高いと、自覚症状のないまま進行していくことになります。
HPVは具体的にどういう感染をするの?
そんなHPVは、生殖器の小さな傷から細胞に入り込むことで感染します。
ここから先は症状の進行について解説するのですが、その前にからだの細胞について触れましょう。
まず前提知識として、
からだを作っている細胞は成長するために大きくなるのではありません。
細胞一つ一つが分裂して数を増やして、成長していきます。
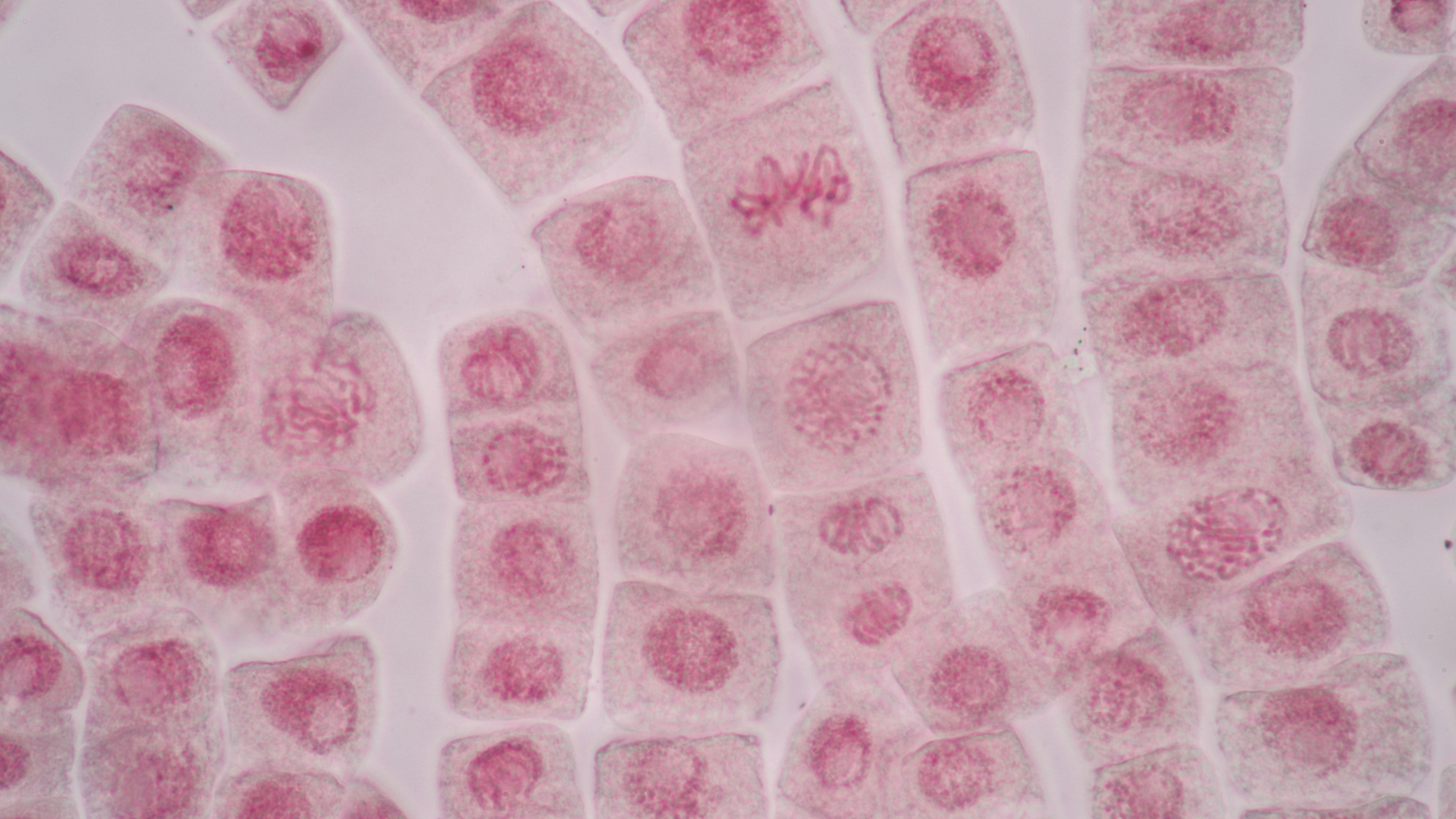
では、小さな傷からHPVが入り込んだ細胞はどうなるのでしょうか?
実は、このウイルスが入り込んだ細胞も、他の細胞と同じ様に分裂して増えるタイミングで一緒に増えていくのです。
ウイルスと共に細胞がどんどん増えていき、異常に増えすぎると細胞の塊となります。
それが、いわゆる腫瘍やイボになっていくわけです。
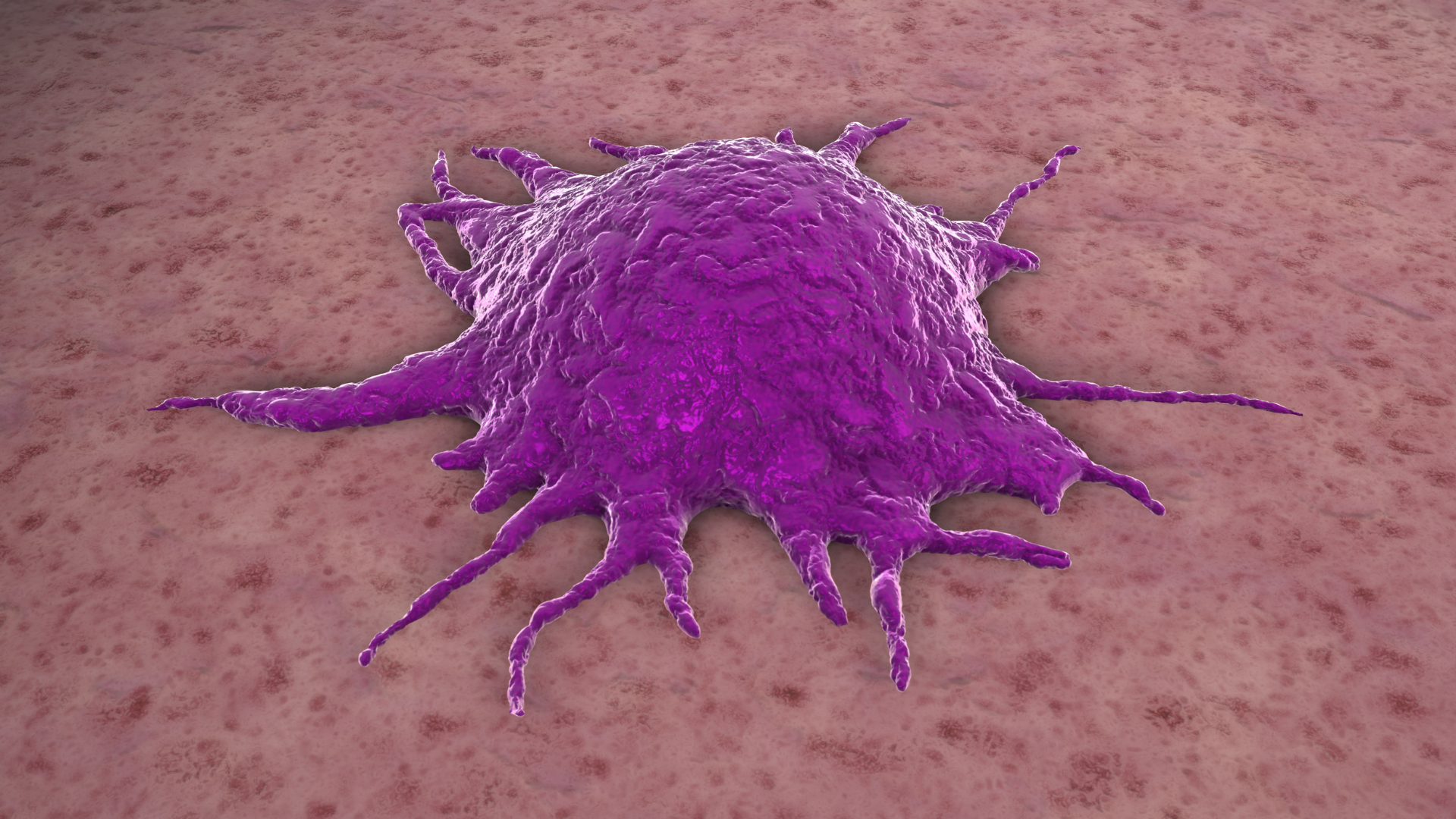
この細胞の塊が、がんになるまでおよそ10〜15年ほどかかると言われており、とてもゆっくりと進行するのが特徴です。
また、自覚症状はほとんどないため、特に早期ではなかなか気づくことはできません。
そのため、進行して大きくなる前に、定期的に検査をして予防することが大切なのです。
HPVを予防するにはどうすればいい?
このようにHPVは、一般的な女性であれば感染する可能性が高く、一定の確率で子宮頸がんに進行する可能性のあるウイルスです。
そのため、乱れた食事や運動不足などでかかる生活習慣病とは異なり、積極的な予防のための行動が重要になります。
ここでは代表的な予防のための行動を二つご紹介します。
HPVの予防法①:ワクチン接種
まずご紹介するのは、HPVへの感染を防ぐ効果のあるワクチン接種です。
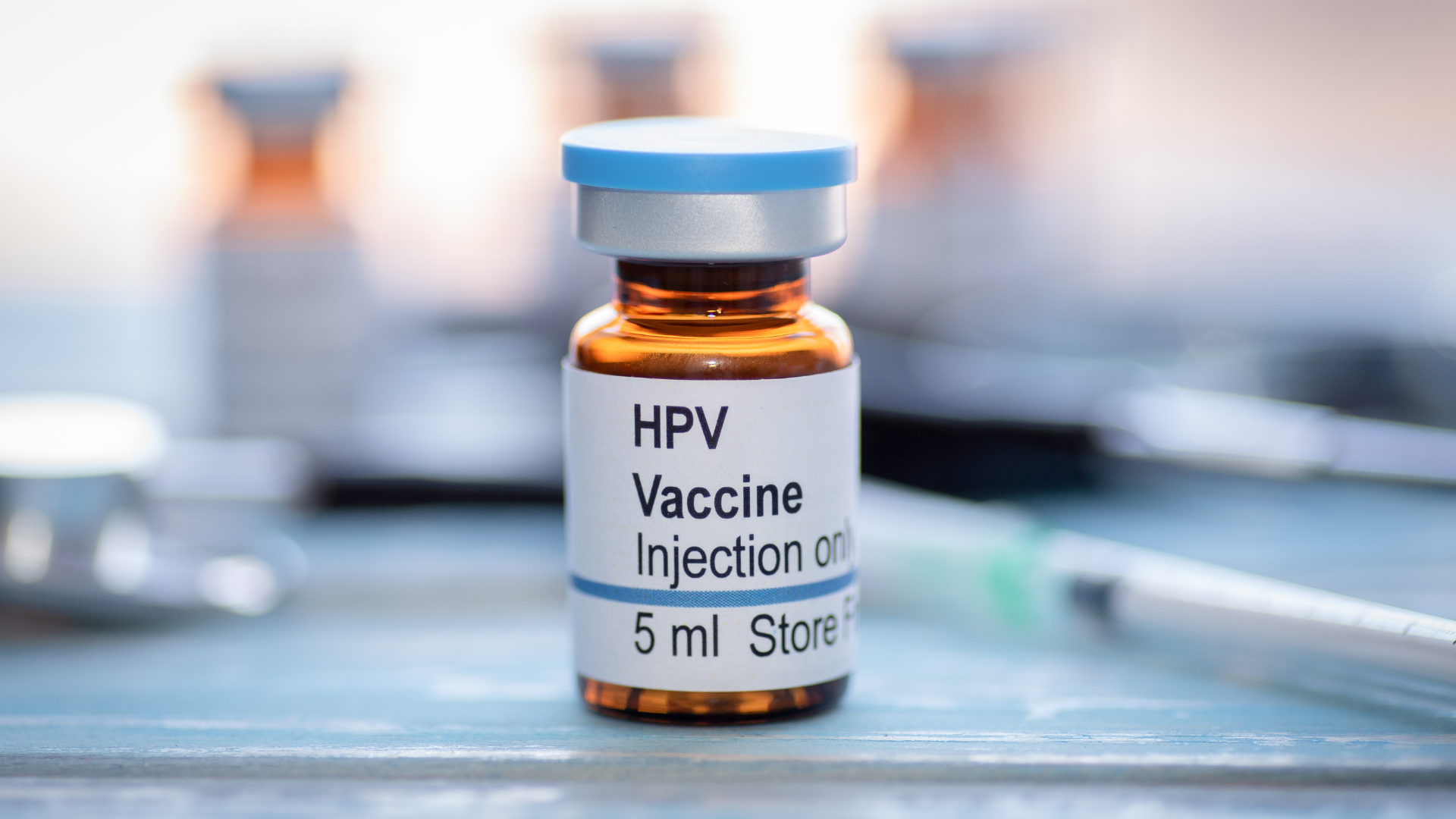
性接触前の小学6年生〜高校1年生の女性は、公費により合計3回の接種を受けることができます。
すでに性交渉の経験がある方でも26歳までは接種が推奨されています。
先述の通り、HPVは遺伝子型が150種類以上あるウイルスですが、それら全てに感染する可能性は非常に低いものです。
また、既に感染していたとしても、新たな感染を防ぐことができると考えられています。
ただし27歳以上の方はライフスタイルによって判断が必要です。
その際はパートナーや専門の医師と相談する必要があります。
HPVの予防法②:定期的な検査
次にご紹介するのは、検査してHPVに感染しているかを調べて、早期の対応をすることです。
検査をする際は、子宮頸部の細胞を採取することになります。

この検査はHPVの感染を予防するというよりは、
HPVへの感染を早期に確認し、病気が進行することを防ぐという意味合いが強いです。
最近は自己採取による郵送検査もあるため、羞恥心を感じることなく気軽に検査することもできます。
HPV検査の具体的な手順
婦人科などの医療機関でHPVの検査を行う際、
細いボールペンくらいの大きさのスポンジや綿棒を挿入し、子宮頸部の細胞を採取します。
具体的な採取の手順は以下の通りです。
・リラックスできる姿勢になる
・スポンジや綿棒を膣の奥にいれてゆっくり擦る
・採取したものは保存液の入った容器に封入
・衛生検査所や病院の病理検査室でウイルスがいるか検査
このように、専門の医療機関でなら簡単に検査を受けることができます。

また羞恥心などで受診に抵抗を感じる方は、
自己採取した組織を専用の容器に入れ、ポストに投函するだけで検査ができる郵送検査も選択肢としてあります。
ちなみに、コンドームを装着することで感染する確率を下げることはできますが、外陰部や肛門までカバーしきれない場所にもウイルスがいることもあるので注意です。
また感染してもピロリ菌のような薬による予防方法がありませんので、定期的な検査が重要になっています。
HPVのリスクを下げるためには定期的な検査が重要!
さてHPVについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?
先述の通り、HPVは一般女性であれば誰にでも感染する可能性があり、その一部が進行して子宮頸がんといった深刻な病気につながっていくものです。
そして、早期においては自覚症状がなく、進行するにつれて生命や生殖機能に大きなリスクを抱えることになります。
しかし、その進行はとてもゆっくりで、定期的な検査による感染の早期発見が重要です。
現在のHPV検査は「子宮頸がん検診」と同じタイミングで採取し検査されることが増えてきています。
今までの子宮頸がん検診は細胞診と言い、採取した細胞を観察しがんになっていないか確認する検査が主流でした。
最近はHPV単独での検査も効果があるとして推奨されているため、どちらかでも検査できれば安心です。
検診の案内が届く自治体によって検診内容が異なりますので、実施前に一度確認してみましょう。
また今スグ、そして手軽に検査したい場合は、自宅でできる郵送検査を利用することもオススメです。
医師による診断がないため検査結果は鵜呑みにはできませんが、感染の有無の参考にするにはとても有効な手段になります。
例えば、下記のリンク先のように、郵送検査は誰でも簡単にネットでの購入が可能です。
HPVへの感染やは、早期発見早期治療が大切です。
子宮頸がんは非常にゆっくり進行するため、2年に1度の検査間隔でも有効です。
デリケートな箇所の検査なので気後れすることもあると思いますが、
ぜひ一度検査をしてみましょう。
それでは、ここまでご覧いただきありがとうございました。
◎参考資料
・国立感染症研究所 ヒトパピローマウイルス感染症 検査マニュアル
https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/hpv_2011.pdf
・厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
・国立がん研究センター社会と健康研究センター「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン」
その他の記事はこちら
弊社の健康チェックイベントを導入していただいた企業のインタビュー記事となっております。
様々な企業と協働しながら、健康に関連する様々な社会課題の解決に取り組んでおります。
弊社が全国で健康イベントを行い、得られた独自情報を公開しています。
検査や病気について、一般の方向けに解説しています。
弊社の予防医療事業部のあゆみについてご紹介します。